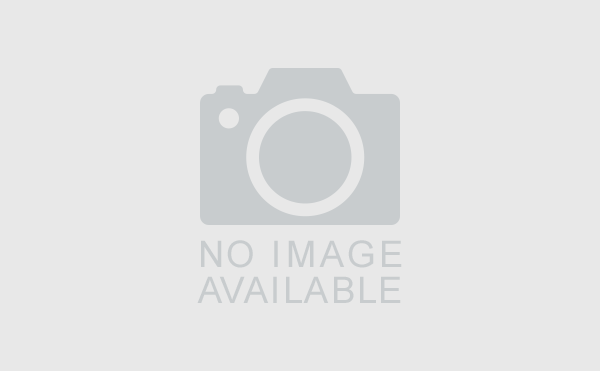【共有不動産】共有者と連絡が取れないときにとれる選択肢とは?
はじめに
「共有名義の不動産なのに、もう一人の共有者と連絡が取れない…」
このような悩みは、実は多くの人が抱えています。放置してしまうと、売却や活用はもちろん、将来的なトラブルにも発展しかねません。
この記事では、共有者と連絡がつかないときに取れる現実的な選択肢と、2021年の民法改正に伴う新制度についても解説します。
【よくあるケース】連絡がつかない共有者とは?
- 相続で不動産を共有した親族
- 離婚後に名義が残っている元配偶者
- 昔の知人や事業パートナー
このような共有者と音信不通になっているケースでは、不動産の処分には原則として全共有者の合意が必要となります。しかし、連絡が取れない相手との共有物分割にはいくつかの選択肢が存在します。
選択肢①:内容証明郵便で正式な連絡を試みる
まずは、内容証明郵便を使って連絡をとるのが基本です。
相手が「受け取っていない」と主張できないため、後の証拠にもなります。
📌送る際のポイント:
- 現在の住所が不明なら住民票で調査
- 弁護士に依頼して送ることで心理的圧力をかける
選択肢②:共有物分割訴訟を提起する。
連絡がつかない共有者に対しては、地方裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起するという方法があります。
🔹ポイント:
- 相手の所在が不明なときには所在不明であることを明らかにしていく可能性あり
選択肢③:2021年民法改正による新制度
2021年民法改正による「所在不明者の共有持分の取得制度」
2021年に改正された民法では、所在不明者の共有持分を取得するための新制度が設けられました。この新制度により、長期間連絡が取れない共有者の持分を取得することができるようになりました。
- 所在地不明者の共有持分の取得:
- 共有不動産の所有者が所在不明であった場合、所定の手続きを経てその共有者の持分を他の共有者が取得できる制度が新たに追加されました。
- 所在不明の共有者に対して、公告を通じて所在確認手続きを行い、一定期間経過後にその持分を取得できるようになります。
- 譲渡制度の活用:
- 所在不明者の持分を強制的に譲渡する手続きが設けられ、これにより、連絡が取れない共有者の持分を他の共有者が譲り受けることが可能となりました。
- 手続きは裁判所を通じて進められ、通知を出してから一定期間経過後に譲渡が成立するため、時間はかかりますが、一定の条件を満たすことでスムーズに持分を取得できます。
選択肢④:持分を第三者に売却する
「自分の持分だけでも手放したい」
そんなときは、不動産業者や持分買取業者に売却する方法もあります。
ただし…
- 売却価格は大幅に下がる
- 共有者との関係悪化のリスクも
⚠️この選択肢は最終手段として慎重に判断すべきです。
選択肢⑤:弁護士に早めに相談する
連絡がつかない相手との共有不動産トラブルは、法律の専門家に頼ることで大きく前進することがあります。
- 内容証明の送付
- 住民票や戸籍からの所在調査
- 訴訟・新制度の代理
こうした対応を、スムーズかつ適法に進められるのが弁護士の強みです。
まとめ
連絡が取れない共有者との不動産問題は、
「そのままにしておく」と、10年後・20年後にさらに大きなトラブルになります。
✅ まずは内容証明で連絡を
✅ 次に訴訟又は所在不明者の持分を取得する制度などの利用へ
✅ 最後の手段として持分売却
そして何より、早めに弁護士に相談することが、最も確実な選択です。
当事務所では、初回相談を無料で行っています。お気軽にご相談ください。
💬「共有名義の不動産で困っている…」
そんなときは、当事務所へお気軽にご相談ください。
📞 無料相談はこちら お問い合わせ▶︎